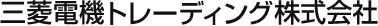2024年のことば
十二月のことば
寒さが身に染みるこの季節、心も体も温まる食べ物が恋しくなります。
旬の野菜や魚介類をたっぷり使った鍋は、栄養も豊富で、寒い冬にはぴったりです。
日本は四方を海に囲まれ、温帯気候で四季の移ろいがはっきりしているため、豊富な食材を用いた独特の食文化が育まれました。和食が2013年12月に世界無形文化遺産に登録されてから、近所の和食屋でも海外からの旅行者をよく見かけるようになりました。
和食の基本はご飯、汁(一汁)、おかず(三菜)であり、出汁のうま味成分が和食の味を支えています。淡泊な味のご飯に、味のある副食、汁物、塩味の多い漬物などを交互に口の中で自分に合った濃さにして食べることも和食の特徴だとか。
和食には多くの長所がある一方、塩分の取り過ぎや、カルシウムが不足しがちという欠点もあるそうです。
食べ過ぎず、飲み過ぎず、体調には気を付けてこの季節ならではの味覚を楽しみ、心も体も温かく過ごしましょう。
十一月のことば
11月の英語「November」は、ラテン語で「9番目の月」を意味する「Novemノウェム」が語源です。Novemは9、berは~番目という意味になります。
11月なのに9番目の月、なんで?大昔に使われていたローマ暦は3月が始まりだったので11月は3月から数えて9番目となります。古代ローマでは1年は10ヶ月と考えられていたそうです。のちに1年は12ヶ月となり、1月と2月が追加されました。(なんで前に足すのか、笑)
さて、今年も残り2ヶ月。年齢を重ねるほど時間の流れを早く感じます。
「時間経過の体感速度は年齢の逆数に比例する」これをジャネの法則といいます。フランスの哲学者、ポール・ジャネさんの発案です。メイクセンスですね。
今年貴方は「自分史上初」をいくつやりましたか?
今年やり残した事ランキング1位は「貯金」、2位は「ダイエット」、3位は「片付け」。
2024年残り2ヶ月、貴方は何をやりますか?
十月のことば
「〇〇の秋」という言葉はいろいろありますが、他の季節ではなく、なぜ秋だけがこう言われるのでしょうか。
それはやはり、何をするにもちょうど良い気候だから。
新年度の始まる春は何かと余裕がなく、夏の暑さが和らぎ、寒さで動きにくくなる冬を迎える前に、いろいろ楽しもうということなのでしょう。
ことに「食欲の秋」は、「実りの秋」からも窺えるように新米をはじめ豊富な美味しい作物、旬のものが味わえる季節を表しています。
日光に当たるほど分泌されるセロトニンは、食欲を抑える効果もあるとか。
日が短くなる秋を迎えると食欲が増すのも道理です。夏バテから回復し、寒い冬に向けて栄養を蓄えなくてはなりません。
必須アミノ酸やDHAなど滋養に富んだサンマは、秋の味覚の代表格。多くの方がその香ばしい匂いや味に秋を想うことでしょう。
日本人の味覚は季節と結びついたところがあります。
だんだんと四季の区別がつきづらくなる日本で、その身に覚えのある季節を旬のものから感じるというのも一興ではないでしょうか。
九月のことば
9月は私の誕生日月です。昔は誕生日のころになると、夜、虫の音が聞こえるようになり、網戸から少しひんやりとした風が吹いて、「秋」を感じていました。
ここ数年は、9月でも夏日が続く状態で、「秋」を感じるのが遅くなっています。
また、9月は台風の季節です。私の生まれた日も台風だったそうです。
今年の「中秋の名月」は9月17日です。また、9月の満月は「Harvest moon」と言われています。これは9月が農作物の収穫(harvest)時期であることからこう呼ばれるようになったそうです。日本でも中秋の名月を愛でる、「お月見」ではおだんご等を供えますね。
台風の季節ですが、中秋の名月には晴れの日を期待して、おだんごをいただきながら、秋の夜長に夏の思い出や、これからのことに想いを馳せたいものです。
八月のことば
今年の大河ドラマでも話題の清少納言は、その名著「枕草子」の中で、日本の夏の風情は特に「夜」に際立つと綴っています。
お盆の時期は休みとなり帰省や旅行をされる方も多いのではないでしょうか。都会の喧騒から離れ、故郷や旅行先で家族や友と、またひとりで過ごす時間。
昼間の暑さから解放され、涼しい風が吹く夜。その静けさの中で、蛍の光が揺らめきます。そして、その静寂を打ち破るように、夜空を彩る花火。
お盆の時期には、灯籠や送り火の灯りが故人を静かに迎え、送り出す夜となります。
これらが織りなす夏の夜の風情は、昼間の活気とは異なる、深い感動を与えてくれます。
そうした夏の夜の楽しみ方を心に留め、酷暑の夏を乗り切っていきたいものです。
七月のことば
いよいよ、パリオリンピックが開催され、世界のトップアスリートによる熱い闘いが始まります。
トップを目指すアスリート達は、日々のトレーニングで自分に誠実にベストを尽くすことや、的確な状況判断と俊敏な反応、何事にもとらわれない心と、いわゆるゾーンに入る集中力が備わっているからこそ、オリンピックという大舞台に立つことができるのでしょう。
ビジネスでも、誠実な対応で信頼を得ること、チャンスを逃さず困難な状況にも適切に対応することは、重要なことです。引退後にビジネスの世界でも成功している選手が多いのは、スポーツを通じこのようなスキルを身に着けていることもあるのではないでしょうか。
また眠れない夜が来そうですが、選手たちを応援し、素晴らしい成果を期待しましょう。
六月のことば
6月に入ると紫陽花の花を公園などでよく見かけます。紫陽花は土の酸性度によって色が変わることは有名ですが、湿度によっても色を変えます。
花言葉も紫陽花の特徴どおり『移り気』や『無常』と悪いイメージがありますが、色ごとにも花言葉を持っており、白が『寛容』、青が『知的』、赤が『強い愛情』となります。
梅雨の時期はジメジメして嫌な気持ちになりますが、紫陽花がつくる自然のアートを見て心を癒してはいかがでしょうか。
五月のことば
5月の始まりはゴールデンウィークの真っ只中で、当社は概ね休日にあたります。ありがたい連休もすぐに終わってしまうのですが、その連休を構成する5月の祝日に少し目を向けてみました。
気になったのはこどもの日。こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する、とありました。5月には母の日もありますが(今年は5月12日)、こどもの日の趣旨には母への感謝も含まれているのですね。
4月は入学、入社、異動、引越しなど変化の多い月で、自身が変わらなくても周りが変わる、目まぐるしくあっという間に終わるウォーミングアップの期間。多くの社会人に春休みはありませんが、ゴールデンウィークを利用してそんな4月を一旦リセット、5月がいよいよ本当のスタートかと思います。
気合いを入れ直して、日に日に上がる気温とともに、調子を上げて行きましょう。
四月のことば
4月と言えば桜。でも最近は温暖化の影響で徐々に開花が早まっているとのこと。その内「3月と言えば桜」と言い始めるときが来るかもしれません。
私は桜を見ると、なぜか何十年も前の自分の中学の入学式を思い出します。通学路に咲く満開の桜の映像とともにその時の感情がフラッシュバックします。少し大人になった気分、何かいいことがありそうな予感、新しい環境に対する不安。そんなごちゃまぜの気持ち。色々な場所での色々な人たちの、その時々の思い出が積み重なって今の桜があるのでしょう。
そうした人々の思い出に支えられて、当分の間は「4月と言えば桜」なのかもしれません。
でもこれは私が住んでいる地域での話。北海道では4月下旬から5月の上旬頃が桜の見頃とのことなので、1ヶ月も差があります。こうしてみると、冒頭の「4月と言えば桜」、これもバイアスのかかった見方なのでしょうね。
もう少し視野を広げて語らないといけませんね。
三月のことば
3月は年度末、学期末、卒業式など節目の季節です。
今年の3月25日は満月、「ワームムーン」と言われています。「ワーム」は英語で芋虫の意味。3月は暖かくなって、地上に芋虫や渡り鳥が戻って来ることにちなんで3月の満月をワームムーンと呼ぶようになったそうです。
いろいろなことが満ちて、次のステージに移っていくこの季節、これまでの自分を振り返り、新しい気持ちで進んでいけるよう、しっかり準備していきましょう。
新しい人・出来事との出会いも楽しみですね。
二月のことば
今年も早いもので2月となりました。
今年は4年に一度のうるう年です。
「4年に一度」と記載しましたが、正確には現在用いられている太陽暦(グレゴリオ暦)では「400年に97回」のうるう年を設けるようです。
西暦1900年、2100年のように100で割り切れる年は通常「平年」となりますが、400で割り切れる年は「うるう年」になります。直近では西暦2000年が400で割り切れるため、400年に一度しかない「特別なうるう年」でした。
もうひとつ、うるう年で気になることは「2月29日生まれの方」に関しての疑問です。「4年に一歳しか歳をとらないの?」、「誕生日のお祝いも4年に一度だけ?」といった点が気になりますが、歳のとり方に関しては法律できちんと決められています。
年齢は、「年齢計算ニ関スル法律」というもので2月29日生まれに限らず誕生日前日が終了する時刻(前日の24時)に1つ歳をとると定められています。ですので、2月29日生まれの方は2月28日の24時に1つ歳をとることになります。
誕生日のお祝いは、平年だと2月28日か3月1日にされていることが多いようです。
2月29日生まれの方も、平年とは違う特別な誕生日を迎えることができますね。
一月のことば
新年、あけましておめでとうございます。
4年ぶりに何の制限もないお正月が還ってきて気兼ねすることなく旅行や新年会を楽しまれた方も多いかと思います。
お正月をゆっくりと楽しむのもよいのですが、「一年の計は元旦にあり」と一年の始まりの時に自分の達成したい目標を考え計画を練るのもよいと思います。
目標は仕事、趣味、学び、健康など人により様々でしょうが、目標があると日々の行動がその方向に向かう手助けになり、新しいことに挑戦したり、興味を持った分野を深めてみたりすることで、知識を広めたり、スキルを磨くことができます。
ただ、計画したことを日々のなかで忘れずに実行することが肝要です。「継続は力なり」の言葉どおり、毎日の小さな努力の積み重ねが、一年後には大きな変化を生むことになります。新年の始まりを自分の成長とポジティブな変化へのスタートとして捉え、この一年を有意義なものにしてゆきましょう。